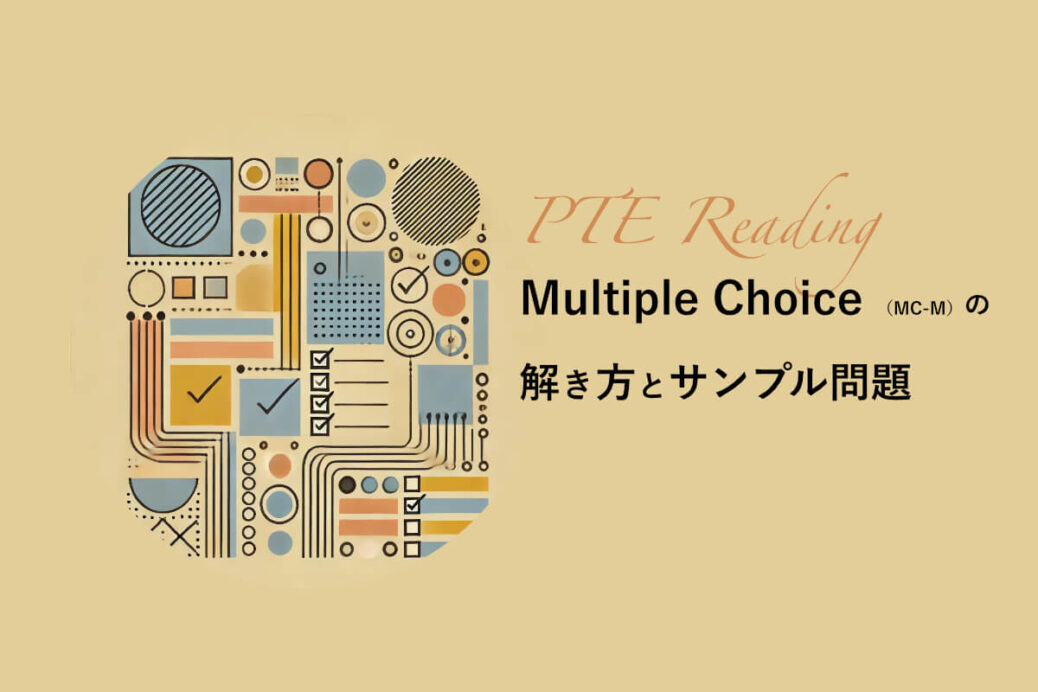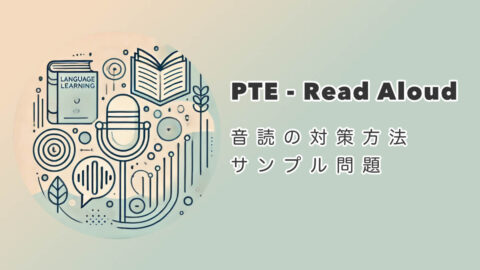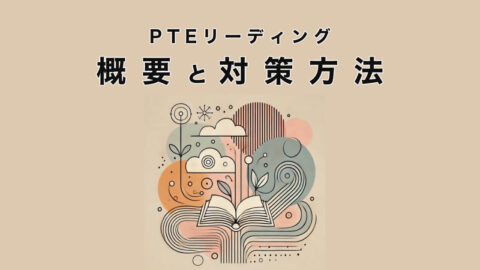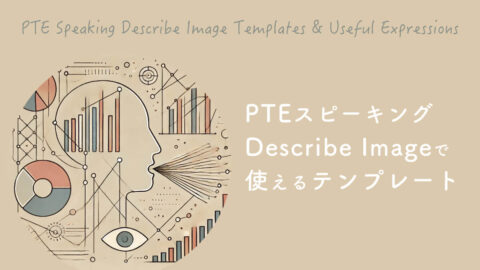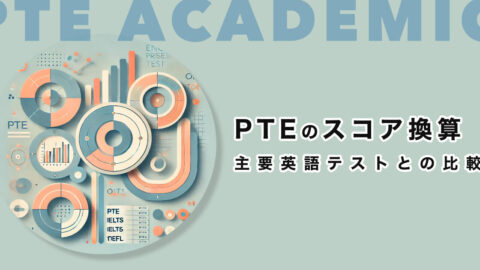こんにちは!SOLO IELTS TOEFLのルークです!
今回の記事では、PTEリーディングセクションのMultiple Choices – Multiple Answers(選択問題:MC-M)の対策方法をサンプル問題付きで解説していきます。
MC-Mは、選択肢の中から複数の正解を選ぶ問題で、PTEリーディングの中でも特に難易度が高い問題の一つです。
しかし、その配点ルールを理解し、危ない橋を渡らないようにすれば着実にスコアが稼げるポイントでもあるので、余力がある場合はしっかりと対策していきましょう。
リーディングで安定したスコアを取るためには、前提として一定量の単語力は必要です。テクニックに先走らず、しっかりと土台を固めていくことも忘れないでください!
それでは詳しく見ていきます。
目次:
Multiple Choices – Multiple Answers(MC-M)の解き方とサンプル問題
まずは、Multiple Choices – Multiple Answersの概要をみてみましょう:
| 問題数 | 2〜3問 |
| 試験内容 | 約200〜300字の文章を読んで、選択肢の中から設問に対応する回答を複数選ぶ。 |
| 正答数 | 1〜3 |
| 採点方法 | 部分点 |
| 読解の目安 | 約2分15秒(1文章) |
着目すべきポイントは、部分点を採用しているという点です。
どういうことかというと、全て正解を選ばずに1つでも正解が選べていればスコアとして加算されるということです。
注意点として、間違った選択肢を選ぶと逆に減点になってしまいます。そのため、自信がない時は選択肢1つだけをクリックした方がリスクヘッジになります。
ちなみに、0点以下になることはないので仮に選んだ選択肢が間違いでも減点される恐れはありません。
正解が複数ある分、正解をひとつ見つけるのはそこまで難しくありません。着実に1点ずつ加点していけばスコアが伸びていきます!
対策① 設問を精読してキーワードを把握する
まず最初に読むべきポイントは、設問で何を問われているのかを正しく理解するということです。
本文を読む時に意識するポイントを理解しておくことで、重要な情報とそうでない情報を区別することができるようになります。
この時に選択肢に目を通す必要はありません。
選択肢から正解を探そうとすると、不必要な情報を繰り返し読解することになりますし、何より文章の流れが掴めないので読解の解像度が低下する恐れがあります。
一点、元々英語を読むのが速い人や帰国子女にとっては、最初に文章全体を読んだ方が効果的な場合があります。絶対ではないので注意して下さい!
対策② キーワードに関連する情報を本文から探す
設問のキーワードを理解したら、本文を “最初から” 読み始め、キーワードに対応する部分を探していきます。
この時にキーワードと関係のない部分はスキミング(サッと読み流す)。キーワードに関連する情報がきたらスキャニング(精読)を行うことを意識しましょう。
読解の精度を情報ごとに区別するイメージです。
注意点は、キーワードという点の情報を探すのではなく、最初から読み始めて文章の流れを掴んで線の情報を捉えていく意識を持つことです。
言語は文脈があって初めて意味が成り立つので、流れ(大局)を掴めると文章の要点や意図をスムーズに汲み取ることができるようになります。
イメージとして車のギアを切り替えているような感じ。重要でない部分はドライブに入れてさっと読み流し、重要な部分はローギアに切り替えてじっくりと意味を掴むとメリハリがつきます!
対策③ 各選択肢と本文の情報を照らし合わせる
本文で対応箇所が見つかったら、その表現と一致しているものを各選択肢を比較して選んでいきます。
選択肢は、
- 本文の情報と一致している(True)
- 本文の情報と異なる(False)
- 本文に書かれていない(Not Given)
の3種類に大きく分かれるので、これらの観点を意識しましょう。
「① 本文に対応するセンテンスと比較すること」と「② 消去法」の2つの観点から選択肢を絞り込むと、安定したスコアリングが可能になります。
消去法のみだと正解を消去するリスクが高くなるので、必ず本文のパラフレーズを探すということを頭の片隅に置いておいて下さい!
コツ:感覚的な “解釈” ではなく書かれている “事実” を比較する
リーディングのスコアが安定しない一番の理由は “感覚的に” 選択肢を選んでしまうことです。
「何となくこれな気がする…」
そう思って何となく回答を続けていても、一向にスコアが安定することはありません。
英語に限らず言語試験は「パラフレーズ(表現の置き換え)」を用いることで、受験生の言語理解力を評価します。
表現が置き換えられているということは、本文にほぼ必ず選択肢と同じ意図・概念の事実が書かれているということです。
イメージとして、大学入学者選抜大学入試(センター試験)の国語のテストを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。
頭の中で思った感覚的なイメージではなく、本文に書かれている事実を読み取る。これを徹底することが、スコアUPにおいて重要なファクターになります。
答えを導く時に「なぜこれが正解になるのか?」を言語化してみるのも効果的です。言語化できない場合は、どこか感覚的に補完している可能性が高いと考えられます!
サンプル問題
上記のテクニックを用いて、以下のサンプル問題を解いてみましょう:
Question:
What factors were involved in the disparity between the calendars of Britain and Europe in the 17th century?
Calendar
“September 2, 1752, was a great day in the history of sleep. That Wednesday evening, millions of British subjects in England and the colonies went peacefully to sleep and did not wake up until twelve days later. Behind this feat of narcoleptic prowess was not some revolutionary hypnotic technique or miraculous pharmaceutical discovered in the West Indies. It was, rather, the British Calendar Act of 1751, which declared the day alter Wednesday 2nd to be Thursday 14th.
Prior to that cataleptic September evening, the official British calendar differed from that of continental Europe by eleven days—that is. September 2 in London was September 13 in Paris, Lisbon, and Berlin. The discrepancy had sprung from Britain’s continued use of the Julian calendar, which had also been the official calendar of Europe from is invention by Julius Caesar (after whom it was named) in 45 B.C, until the decree of Pope Gregory XIII in 1582.
Caesar’s calendar, which consisted of eleven months of 30 or 31 days and a 28-day February (extended to 29 days every fourth year), was actually quite accurate: it erred from the real solar calendar by only 11 1/2 minutes a year. After centuries, though, even a small inaccuracy like this adds up. By the sixteenth century, it had put the Julian calendar behind the solar one by 10 days.
In Europe, in 1582, Pope Gregory XIII ordered the advancement of the Julian calendar by 10 days and introduced a new corrective device to curb further error, century years such as 1700 or 1800 would no longer be counted as leap years, unless they were (like 1600 or 2000) divisible by 400.”
Question:
What factors were involved in the disparity between the calendars of Britain and Europe in the 17th century?
A: the provisions of the British Calendar Act of 1751
B: Britain’s continued use of the Julian calendar
C: the accrual of very minor differences between the calendar used in Britain and real solar events
D: the failure to include years divisible by four as leap years
E: the decree of Pope Gregory XIII
F: revolutionary ideas which had emerged from the West Indies
G. Britain’s use of a calendar consisting of twelve months rather than eleven
まず設問を読んでどの情報に焦点を当てるのかを理解します。
すると「イギリスとヨーロッパにおけるカレンダーの違い」について書かれている情報を読解するべきであることが前提として分かります。
その上で、本文を読み進めていきます。
読み進めると “Britain” のカレンダーの置き換えとして “Julian Calender” や “Caesar’s calendar” という表現が含まれるセンテンスが見つかると思います。
そこが、イギリスのカレンダーの特徴を述べている文章であると考えられるので、その部分に焦点を当てて選択肢の情報と対比していきます。
すると、マーカーを引いたポイントから「B・C・E」に同じ表現が書かれていると判断することができます。
このように、対応するキーワードを理解した上で、読解を始めると読み返しの数を抑えることができ、結果的により早い読解が身についてきます。
まとめ
今回の記事の内容をまとめると、
- 設問→本文→選択肢の順番に読み進める
- 情報ごとにスキミングとスキャニングの切り替えを行う
- 自信がない時は1つだけ選択肢を選ぶ
上記3点がポイントです。
リーディングを安定して行うためには、基礎の語彙力と文法力は必須になるので、わからない単語が5つ以上出てくる場合は単語学習も並行して行うようにしましょう。
ただ、MC-MはPTEのリーディングの中でもトップクラスに難しい問題です。
そのため対策の最初に行うべきものというよりは、より高いスコアを安定させるための対策になると思います。
まず最初は基礎固めをしつつ、リスニング・スピーキングといった音声情報関連の対策に焦点を当てても戦略としてはよいかもしれません。
PTEに関する概要や傾向は以下の記事でまとめていますので、ご確認ください:
記事を最後までよんでいただき、ありがとうございました。
何かご質問などあれば、お気軽にご連絡ください!